日本で人間関係が息苦しく感じること、
ありませんか?
私がオーストラリアに留学していた時
ふと気づいたことがあります。
それは、
「意見が違っても人間関係は終わらない」という安心感。
あの頃の友人たちとの関係が
今思えばとても心地よかったのです。
なぜそう感じたのか。
それは日本との文化の違いだけでなく
自分の中にあった
“人付き合いの前提”が
変わっていったからかもしれません。
Contents
オーストラリアで感じた「健やかな対話」
オーストラリアでは、
意見が対立してもそのまま受け入れ合う空気がありました。
「私はこう思う」
「自分は違うと思うよ何故ならー」
そんなふうに、
お互いが言葉を交わすこと自体が健やかで
時にはそれが建設的な議論に
つながっていくこともありました。
たとえば
一つの議題で意見が食い違っても
その場限りの意見でしかなくて、
「じゃあ次の話」と切り替えられる。
それは、
あなただから言えるという事を前提に
“人と意見を切り離して見ている”文化
のように感じました。
私が特に印象的だったのは、
「対立をきっかけにより良い意見に昇華させる」姿勢。
対話を通して考えが磨かれていく感覚があり
人間関係もそれにともなって
深まっていくように思えました。
イタリア人のマリオ
よく思い出すのは、
イタリア人のマリオのこと。
語学学校で出会った超陽気なおじさんで
毎日のように
「放課後は何してんの?」って聞いてきて
私は、「図書館行くよ」と答える。
すると決まってこう言うんです。
「語学学びに来てるなら、放課後は飲み会パーティだろうがよー!」
って(笑)
とにかく明るくて、
人を巻き込む力がすごかった。
でもね、断られてもまったく気にしないんです。
きっと、彼のポリシーは、
“目的が合致したときは、一緒に楽しめればいい”
自分の主張ははっきり伝えるけど、
他人の意見は尊重する。
断った人を仲間外れにすることも一切しない。
日本だったら、
「付き合い悪い」なんて言われて
輪から外されてしまうようなことも
マリオはサラッと流して
また翌日には笑顔で
「飲み行こうぜー!」と声をかけてくれる。
当時は全く何とも思っていませんでしたが、
この年になって、あの軽やかさが
私にはすごく心地よかったんだな。って気付きました。

日本の「空気を読む」圧力とママ友の世界
日本に戻ってから、
社会人になり、結婚し、出産。
そしていわゆる「ママ友」が出来てから
「友達」の関係に違和感を感じるようになりました。
たとえ何かに疑問を感じていても、
それとなく話を合わせるのが“常識”。
ちょっとでも本音を出すと空気がピリついて、
最悪陰で噂されることもある。
最初は私も「合わせる努力」をしていたけれど
あるときふと、こう思ったんです。
むしろ、違いを見せないようにすることで、
どこか“薄っぺらく安全な関係”に収まっていく気がする。
でも、それで本当にこのままでいいのかな?
たとえばあるランチ会。
話題は、
夫の愚痴や子どもの「できない」自慢ばかり。
「うちの夫、本当に何にもできなくてさ〜」
「うちの子、〇〇が全然ダメで〜」
そういう話に対して、
「わかる〜うちもだよ〜」と頷き合う空気…
そのとき私は、
“ああ、私も同じでよかった”という
妙な安心感を共有しているだけのように感じて
なんだかモヤモヤしたんです。
共感し合っているようで、実は
「お互いに深く踏み込まないことで安心している」
だけなのかもしれない。
それって本当に意味がある事なんだろうか?
私が求めている“信頼関係”なんだろうか?
って。
表面的には穏やかでも、
本音の対話がなく、
気まずさを避けることばかり優先される。
それで築かれる関係が
自分にとって心地いいわけがないと気づいたんです。
だったら、たとえ
時に意見がぶつかることがあっても
お互いの考えや違いを受け止め合える関係のほうが、
ずっといい。
そのプロセスこそが
信頼につながっていくんじゃないか
と思うようになりました。
意見の合わない人を排除していたら
世界中すべての人が敵になってしまう。
敵になりたくないから、
意見を言わない。これじゃ、
本末転倒だと思ったんです。
テーマごとに是々非々でつながる人間関係へ
この経験をきっかけに
私は人との距離の取り方を見直すようになりました。
今では、
「テーマごとに是々非々」でつながる関係性を大事にしています。
ある話題では合わなくても、
別の話題では楽しく話せる。
ひとつの意見の違いだけで
「この人とは合わない」と切り捨てるのではなく、
その都度、そのテーマについてどう感じるかで
関わり方を柔軟に変える。
そうすることで、
無理なく関係が続くようになったし
「全部を共有しなくても、部分的に心地よくつながれる」って
すごく自由で心地いいと思えるようになったなんですよね。
ただし、これは
“メリット・デメリットで人を選ぶ”という
打算的なものとは全く違います。
人の“人間性”って、
会話の節々やちょっとした行動の中ににじみ出るもの。
だから、
最近は初対面でも
「この人とは心地よく付き合えそうだな」とか
「この人はちょっと違うかな」って
感覚的にわかるようになってきた気がします。
表面的な「いい人」かどうかよりも、
“違いを扱える人かどうか” が、
今の私にとってはとても大事。
「この人とは長く付き合えそうだな」と思えるのは、
意見の違いを敬意をもってきちんと話せる人です。

まとめ:信頼のない人との時間、それって本当に必要?
人との関係をどう築くか。
それは、
自分の心地よさをどう守るかともつながっている。
オーストラリアでの経験を通じて私は、
「意見が違っても関係は壊れない」
という安心感を知りました。
それに比べ、日本では
「空気を読むこと」が優先され
違いを出さないようにする関係の中で
自分の本音はどんどん後回しになっていった。
だけどあるとき思ったんです。
信頼のない人と、
無理して同じ時間を過ごす意味ってあるんだろうか?と。
その答えは、私の中ではもうハッキリしていて
これからは
「違っていても、尊重し合える関係」
を選んでいきたいと思っています。
全部を共有できなくてもいい。
でも、
「この話題はちゃんと話せる」
「違っても受け止めてくれる」
そう感じられる人との関係には
安心と成長があります。
だからこそ、
これからは自分の感覚に素直になって
心地よく関われる人を、大切にしていきたい。
40代に入ってそんな風に
考えられるようになりました。
“違い”を恐れずに関われる関係こそ
本当の意味で信頼が育つ場所だと感じています。
もし人間関係で悩んでいる方がいたら
こんな考え方もあるよ。
というヒントになれば幸いです。
今回もお読みいただき、ありがとうございました!
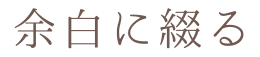




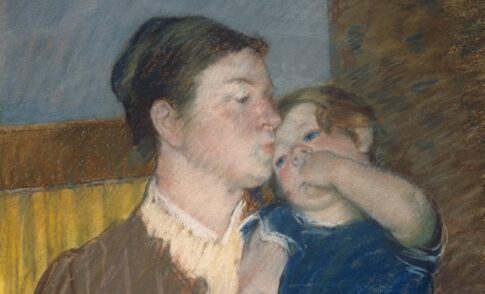


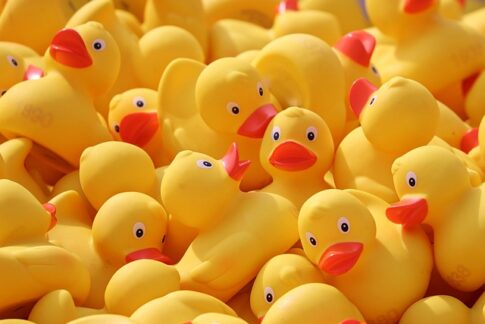



コメントを残す