ある朝、
次男が見た夢を話してくれました。
「牛とすごく仲良くなって、でも
その牛が牛肉にするため殺されちゃうことを知って、
だから牛を盗んで、でも、盗んだから刑務所に入って。
刑務所から出てきて家に帰った時の最初のご飯がステーキで、
牛を殺してステーキにした親を殺す夢だった」
・・・と。
一瞬、言葉を失いました。
残虐な内容に聞こえるかもしれませんが、
話す次男の表情は、どこか悲しげで
複雑な思いを抱えているように見えました。
この夢を聞いたとき
最初に浮かんだのは「怖い」という感情ではなく、
「何か心に抱えているのかもしれない」
という直感でした。
夢の内容には、
誰かを守りたい気持ちと
理不尽な現実への怒り
そして、
そのはけ口としての攻撃性が
交錯しているように感じられました。
これは、
言葉にはできない心の葛藤が
夢という形で表れたのではないか。
そんなふうに受け止めたのです。
Contents
頑張り屋な次男。でも、少し歯がゆい
次男は、本当に頑張り屋です。
やると決めたことには一生懸命に取り組み
真面目で、
自分のペースでコツコツ努力を重ねるタイプです。
ただ、
頑張り方が少し空回りしていることもあります。
「ちょっとそれは間違ってるな・・・」
「それは今やらなくてもいいのでは?」
「もっと楽な方法もあるのに」
と、 親として思うことも少なくありません。
しかし、
本人は本人なりにベストを尽くしているのです。
だからこそ、
私は今、なるべく口を出さずに見守るようにしています。
「自分で気づいて、自分で学んでほしい」
という思いからです。
とはいえ、
そのプロセスは非常に歯がゆいものでもあります。
目の前にヒントがあるのに、届きそうで届かない。
でも、だからこそ
「待つ力」も親にとって大切なのかもしれないと感じるのです。

夢と、牛乳パックへのグーパンチ
そんな次男が語った、少し不穏な夢。
普段の彼からは想像がつかないような内容でした。
そして、その翌日。
学校の先生から
「給食の時間に牛乳パックをグーパンチした」との連絡が。
この報告を聞いた瞬間
私は「やっぱり…」と思いました。
夢に出てきた複雑な感情と
現実の中で起きた突発的な行動。
この二つがリンクしているように感じたのです。
きっと、日々の生活の中で感じる
“うまくいかないこと”や“期待とのズレ”のようなものが
少しずつ積み重なっていたのでしょう。
そして、それが
「夢」という無意識の中で表現され、
「グーパンチ」という行動として
噴き出したのかもしれません。
子どもは、自分の心にたまった感情を
言葉ではなく別の形で表現することがあります。
そのサインに気づけるかどうかは、
私たち親の観察力にかかっているのかもしれません。
((このことでの気付きはまた後日記事にしてみたいと思います。))
「頑張っているのにうまくいかない」ことのつらさ
子どもにとって、
「頑張っているのに結果が出ない」状況は
言葉にできないほどのストレスになることがあります。
特に真面目な子どもほど、
「どうして?」「自分はダメなのかもしれない」と
納得できず、自己否定に近い感情を抱いてしまうことがあります。
というのも、
私自身がそうだったからです。
私の場合は
母親に褒めてほしい一心でいろんなことを頑張っていました。
でも、
うまくいって当たり前
うまくいかなければ叱責される
という毎日。
今思えば、
自由よりも“親の期待”の中で生きていたような小学生時代だったと思います。
(このことはまた別の機会に)
ずっと誰かの評価に応えようと
自分を押し込めて頑張ってしまっていたのです…。
だからこそ、
次男の「頑張っているのにうまくいかない」気持ちには
痛いほど共感してしまいます。
こういう意味では
私自身はありのままの子供の姿を受け入れてあげたい
と思っている反面、
親の期待に添いたいと思わせてしまっていたのかもしれない
という罪悪感に苛まれますに苛まれることもあります。
「どうしてわかってもらえないんだろう」
「自分なりに頑張っているのに」
そんな心の声が、夢という形になったり
行動として出たりするのかもしれません。
大人でも頑張っているのに空回りすることはあります。
ただ、
子どもはその気持ちを外に出す方法を、
まだうまく持っていません。
だからこそ、
そのストレスが「夢」や「突発的な行動」として
現れるのではないかと思います。
「正す」のではなく、「感じ取る」
では、
親としてどう接するべきだったのでしょうか。
アドバイスすること?
注意すること? 励ますこと?
最近の私は、
どれも少し違うと感じています。
私の母は 私が小学生の時、
「ちゃんとしないから、こんな結果になった」
とだけ言い放ち、
後は自分で考えて
何とか結果を出せと言わんばかりの
鬼上司のようでした。
当時の私は、
自分の感じていることや不安を
安心して伝えることができなかったように思います。
だからこそ、子どもには同じ思いをさせたくない
というのが私の根っこにあるのかもしれません。
今、私が子どもたちに大事にしてあげたいのは
「そばにいて、感じ取ること」です。
正すのではなく
「あなたは今、そういう気持ちなんだね」と
そのままを受け止めること。
言葉にできない思いを
表情やしぐさから感じ取ること。
子どもは、
自分の気持ちを言葉にすることが難しい一方で、
大人が自分をどう見ているかを敏感に察知しています。
だからこそ、
黙っていても
子どものペースに合わせてただそばにいる。
それだけでも
子どもにとっては大きな安心になるのだと思います。
何故なら、私が子どもの時
母親にそうしてほしかったから。
「ちゃんと話してくれないとわからない」
と大人は言いますが
子どもだって
「ちゃんと聴いてくれそうにないから言えない」
と思っているかもしれません。
話せる環境を作るのは、
やっぱり大人の側の役割なんですよね。

整えるのは、まず親の“受け止め方”
子育てというのは、
「子どもを育てること」と同時に
「親自身が育てられること」の連続だと感じます。
感情を整えることも、
思考を整えることも、
行動を整えることも。
結局は
“自分”次第なのだと思っています。
そんな中で、
私の心に深く残っている言葉があります。
フランス柔道界のレジェンド、テディ・リネール選手が、
「試合前には家族にそばにいてほしい。
ニコニコして笑っていてくれるだけでいい」
と語っていたことです。
この言葉を聞いたとき
私はハッとさせられました。
子どもにとって母の存在とは
“ 何かをする人” ではなく、
“ ただそこにいることで安心をくれる人 ”
と、 改めて気づかされたのです。
私たち親はつい
何か言葉をかけなければ、
アドバイスをしなければ、
正しい方向へ導かなければ ――と思ってしまいます。
でも、実は
「笑って、ただそばにいてくれるだけでいい」
それだけで
子どもにとっては十分なのかもしれません。
整えるべきは、まず自分の心。
親が落ち着いていれば
その安心感は子どもに伝わります。
逆に、親が不安定であれば
その揺らぎもまた
敏感に伝わってしまうのです。
だからこそ私は
自分自身の「受け止め方」を整えて
言葉よりも存在そのもので
子どもに安心感を届けられる母でありたいと思っています。
子どもが「自分で気づく」ためにできること
私が次男にしてあげたいのは
「正解を与えること」ではありません。
それよりも
「自分で気づけるように、
安心して失敗できる場所をつくること」
が大切だと感じています。
そして、 彼が何かにぶつかったとき
「ひとりじゃないよ」と
言葉にしなくても伝わるような距離感で、
そっと見守っていたいと思います。
完璧な親にはなれなくても
こうして日々の気づきを大切にしながら
少しずつ“整えて”いけたらいいなと感じています。
今回も、最後までお読みいただきありがとうございました。
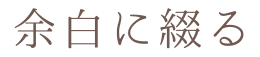




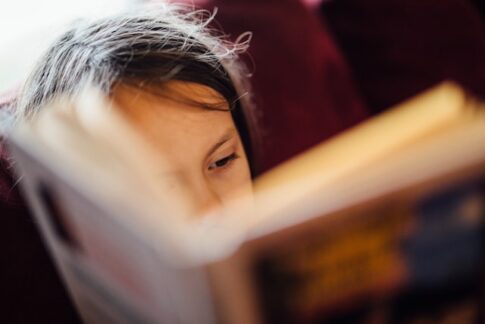






コメントを残す