「これ、本当に小学校で起きたことなの?」
そんな思いが
頭から離れない出来事がありました。
息子が“ある本”について
感想を言ったことをきっかけに、
学校で理不尽な謝罪を求められました。
そこには、子どもの気持ちを置き去りにした
“教育”という名の”大人の事情”が見えました。
Contents
出来事の概要
登場人物は、息子(小4)とクラスの子たち。
ある日、息子が友人Bに
「コロ〇〇コミックについてどう思う?」
と聞かれました。
それに対して、息子は素直に
「自分はあまり面白くないと思う」
と答えたんです。
ところがその会話を
近くで聞いていた別の子(Aくん)が突然割り込み、
「○○コミックの悪口を言った!」
と先生に“報告”。
その結果、先生は状況を確認しないまま
「人の好きなものを否定するのはよくない。
傷つけたんだから謝りなさい」と
息子に謝罪を命じたのです。
正直に”感想”を答えた子どもが
謝らなきゃいけなかったなんて…
教育の場で起きた、静かな暴力のような出来事でした。
先生の対応に感じた強い違和感
今回の出来事で、最初に感じたのは
「なんだかおかしい」という
説明のつかない違和感でした。
話を整理すると
息子はただ「コロ〇〇コミックってどう思う?」と聞かれ
その質問に対して「面白くないと思う」と、
自分の正直な気持ちを返しただけ。
それだけの出来事だったはずです。
ところが、近くにいた別の子どもが
それを“悪口”と受け取り、先生に伝えた。
そして先生は、
話の流れも背景も確認せず、
うちの子に「謝りなさい」と指導したのです。
私はその話を聞いた瞬間
「なぜ?」
という疑問でいっぱいになりました。
うちの子は誰かを貶めようとしたわけではない。
ただ
「好きではない」と感想を言っただけ。
しかも、
それは誰かを否定する意図ではなく
「好きかどうか」を尋ねられたから
正直に答えたにすぎません。
それを
「人の気持ちを傷つけたから謝れ」
と指導するというのは、
あまりに一方的で短絡的すぎる。
先生が言い分は、こうです。
「人には好きなものがあって、それを否定されると傷つくことがある。
だから、言い方に気をつけようね」
このように説明しようとしていたようですが
私は、その時点で先生が
根本の問題を理解していないと感じました。
今回の息子の発言は
誰かを非難するためのものではなく
単なる感想。
それを一方的に、
先生という立場の方が
「好きなものを否定する=悪いこと」という
単純な図式に当てはめてしまった
ということに
強い違和感と不信感を持ちました。
子どもたちのやりとりはもっと複雑で繊細です。
そこを汲み取らずに、表面的に
「謝らせる」ことだけで片付けようとしたこの対応は
教育的配慮とは到底思えませんでした。
論点は、「表現の仕方」ではなく
「感想を答えただけで謝らされる理不尽さ」
だったはずなのに……
先生の対応はそれをまったく理解していないように感じました。

見えない圧力にさらされる子どもたち
今回の件で、私が一番ゾッとしたのは――
息子に「謝れ」と言った言葉の背後に、
“空気を乱すな”という圧力が透けて見えたことです。
先生の意図は、もしかしたら
「場をおさめたい」だけだったのかもしれない。
でも、それが結果的に、
「本音を言う子が悪者になる」
という空気を生み出してしまっていた。
これは教育ではなく
ただの
“精神的圧力による支配”です。
うちの子は、ただ聞かれたから
正直な気持ちを答えただけ。
それが、
「誰かの好きなものを否定した悪者」になり
しかも
事実確認もされないまま、謝罪を強要された。
この流れの裏にあったのは
うるさい児童からの間違った事実
を収めるために
真実を”無視する”という先生の姿勢
だったと感じます。
学校の先生にとって
「揉めごと」は扱いづらく
できれば
早く終わらせたいことなのかもしれません。
でも
だからといって
一方的に「悪かった子」を決めつけて
謝らせて終わらせるようなやり方が
教育の名のもとにまかり通っているとしたら――
それは
”いじめ”のようなもの
とは言えないでしょうか。
今回の先生の対応はまさに
「空気を乱さずに、みんな仲良くね」
という建前に従って、
“見なかったこと”にしようとした行動に見えました。
でも、そのやり方こそが
子どもにとっては
大きな“見えない圧力”だと思うんです。
学校で子どもたちは、
言われなくても感じ取っています。
「こういう時は、自分の気持ちよりまわりの空気を大事にしなきゃいけないんだな」
「誰かが“傷ついた”って言ったら、こっちが悪いことにされるんだな」
「本当のことを言うと、面倒なことになるから黙っておこう」
こうして、子どもたちは
“正直に話すこと”を手放して、
“波風を立てない術”だけを身につけていく…
それが本当に、
私たち親や、大人たちが
正しいと思う教育なんでしょうか?
さらに問題だと感じたのは、
この、
「いい子ちゃんでいましょうね」
という空気を
先生自身が “正しい”と信じて
無自覚に押しつけていること。
クラスを“管理”する立場として、
静かで平和な毎日を作るのが
先生の役目だ・・・
というプレッシャーもあるのでしょう。
だからこそ
多少理不尽でも
「聞き分けの良いB君が謝って、A君が満足すればOK」と
考えてしまったのかもしれません。
でも、
目の前にいるのは
“管理される大人の集団”ではなく
ひとりひとりが発達段階の
ひとりひとりが違う背景と感情を持った
子どもたち。
誰かの声だけを聞いて
誰かの気持ちをないがしろにするような指導に、
子どもたちは敏感に傷つきます。
今回の息子のように
「ただ聞かれたことに答えた」だけで
悪者にされた体験。
子どもにとっては
「もう本音を言わない方がいいんだ」という
強い学習になってしまうと思います。
それが積み重なれば、
自分の考えや感情を伝える力は育たず
やがて
「他人に合わせることしかできない子」
になってしまうかもしれません。
「空気を守るために、事実を無視する」
「みんながいい子に見えるように、面倒な子を黙らせる」
これは、子どもにとっての“教育”ではなく
ただの“大人の都合”でしかないと思うのは
私だけでしょうか。
私たち親がすべきことは、
こうした“空気の圧力”に気づき
子どもの心が押しつぶされる前に
適切にサポートすることだと思います。
親として感じた怒りと悲しみ
正直に言うと、
先生とのやりとりの中で
私は強い怒りと深い悲しみの両方を感じました。
まず怒りについて。
自分の子どもが、何も悪いことをしていないのに
「謝らされた」ということ。
それだけでも親としては相当腹が立ちます。
でも、それ以上に問題なのは、その謝罪が
「事実を確認しないまま」強いられたものだったということです。
子どもにとって
自分の気持ちを言葉にして表現することは
とても勇気のいることです。
とくに周りに“空気を読む”ことを求められる
学校という場では、なおさらです。
そんな中で、
息子はきちんと自分の考えを持ち
聞かれたから答えた。
それだけなのに、
なぜ謝らなければいけなかったのか。
先生は、状況は確認していないけれど、
「誰かの好きなものを否定するのは良くないことだから」。
私は
「それって、教育として本当に正しい姿勢なんですか?」
と問いかけたくなりました。
そして同時に、強い悲しみも感じました。
子どもは、聞かれたことに対して
正直に答えただけだったのに。
にもかかわらず、
「人を傷つけた加害者」のような扱いを受け
「悪いことをした子」として謝罪を命じられた。
その体験は、きっと息子の中に
「本当のことを言うと損をする」
「面倒ごとになるなら何も言わない方がいい」という
望ましくない学びとして残ってしまうでしょう。
子どもにそんな体験をさせたくて
学校に送り出しているわけではありません。
「とにかく波風を立てない」ことは
学校の理想かもしれません。
しかし、
それが学校運営の目的ではないはずです。
本来であれば、
子どもたち一人ひとりの声や思いを丁寧に受け止め
対話の中からお互いを理解していくことが
教育の本質であるはず。
それを見失った学校の対応には
やはり怒りを感じざるを得ません。

こんなとき、親はどうすればいいのか
① 子どもの話をじっくり、先に聞く
まず何より、
子どもの言葉を信じてあげること。
「先生に言われたから謝った」という言葉の裏には
必ず葛藤や不安があると思っています。
「あなたの気持ちは間違ってないよ」
「どう感じたのか教えてくれてありがとう」
この言葉だけでも、子どもは救われます。
② 学校には冷静に、でもはっきり伝える
「大人同士の建前の会話」にならないように、
親として見逃せないポイントは
遠慮せず伝えるべきだと私は思います。
- 事実確認をせずに謝罪させたのは、教育上おかしい
- 感想を聞かれて答えたことは、悪口とは違う
- “言い方の問題”にすり替えるのは、責任逃れに聞こえる
相手が防御モードになっていても
子どもの心を守るのは親だけです。
③ 今後、再発を防ぐためにできること
先生の性格や体質によっては
根本的な改善を期待するのが難しいこともあります。
(今回のうちの場合です)
でも、以下の点は「お願い」ではなく
「要望」として伝えて
良いものではないでしょうか。
- 今後、他の子が同様の「告げ口」をした場合、まず事実を確認してほしい
- 子どもたちの価値観の違いを学び合う時間を、ぜひクラス内で持ってほしい
- 子どもが安心して生活できるように“本音を言えない空気”にならないよう配慮してほしい
こんなところでしょうか。
さいごに
書きながら、少し
熱くなってしまいました。
「感想を正直に言ったら謝らされた」――
こんな経験は、子どもにとって
理不尽でしかありません。
でも、親がしっかり寄り添い、
これが起こりうる社会である事実も学ばせつつ、
学校とも丁寧に向き合うことで
子どもにとって、これは
「自分を信じてくれる大人がいる」と
感じられる経験にもなります。
もし、同じような状況に悩んでいる親御さんがいたら、
どうか、
「先生に嫌われたくない」とか
「波風を立てたくない」と我慢しすぎず、
お子さんの心を守るために必要な事であれば
一歩踏み出してほしいと思います。
また、
良かったことではありませんが、
社会の理不尽さを
早い段階から学べたと思って
淡々と対応していきましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
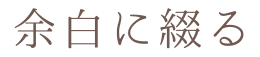





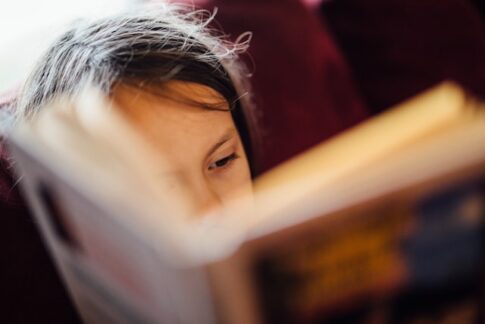
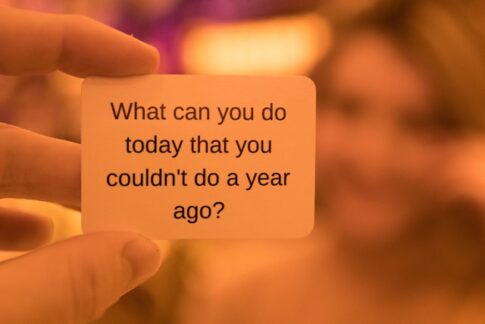




コメントを残す