中学受験を見据えて塾に通い始めたけれど
「本当にこの塾でよかったのかな」と迷う瞬間は
どのご家庭にもあるのではないでしょうか。
今回は、小4の我が子が
日能研から早稲田アカデミーに転塾することになった経緯と
その中で親として何を感じ、どう決断したか
を記録しておこうと思います。
転塾は、決して簡単な決断ではありませんでした。
けれど、今思うのは
「塾選びは、子どもの個性や今の状態に合っているかが何よりも大事だ」ということ。
少しでも、同じように悩んでいる方の参考になれば幸いです。
Contents
日能研に入った理由:自然な流れと、安心感のあるスタート
中学受験を意識し始めたとき
我が家では特に迷うことなく
まずは日能研に入塾しました。
選んだ理由はとてもシンプルで、
- 長男が日能研に通っていたため、なんとなく馴染みがあったこと
- 自宅から近く、通塾の負担が少なかったこと
この2点が大きなポイントでした。
ただ、もちろんそれだけではありません。
日能研は他の進学塾に比べて
進み方がマイルドというか…
同じ単元を何度も繰り返ししてくれるので、
やり直しや間違い直しが中途半端で終わっていても
何となく安心できるんですよね。
それに加えて、
小4の時点で私たちが求めていたのは
以下のような環境でした。
- 基礎力をしっかり固めてくれるカリキュラム
- 「やる気」に寄り添いながら丁寧に導いてくれる先生の存在
早期にトップレベルを目指すというよりは
“勉強を前向きに捉える力”を育てたい
という気持ちが強かったように思います。
そして実際に通ってみて良かったと感じたのは
同じ小学校の友達が何人か通っていたこと。
その中でも、
トップクラスの成績を出している子がいたので
我が子にとっては大きな刺激となりました。
日能研へのモヤモヤ
転塾を真剣に考えるようになったのは
日能研に通い始めて半年ほどが経ったころのことでした。
きっかけは、
成績の下降とそれに対する塾の対応に
親としての違和感が積もっていったことです。
最初は「少し調子が悪いだけかな」
と見守っていたのですが、
だんだんと本人の表情にも不安や諦めの色が見えてきました。
一番大きかったのは、以下のような点です
フォローの少なさ
成績を不満に思っている息子に対して
塾からのフォローやアドバイスがまったくない
ということに疑問を持ちました。
「このままではまずいかもしれない」
と思った私たちが、先生に相談すると、
一旦は「本人に声掛けしてみます!」
とは言っていただけるんですが…
当の本人にはあまり届いていない様子。
また、
本人が分からない問題を質問しようとしても
質問のタイミングに先生がいないことが多く
子ども自身のやる気が削がれてしまった事も何度かありました。
授業スタイルへの違和感
授業は淡々と進み
理解があいまいなままでもそのまんま
な雰囲気がありました。
日能研は復習と自学習に力をいれている
と言われてしまえばそれまでなのですが…
復習をちゃっとやる環境が提供されていないというか
本人のやる気を受け止めてくれはしないんだな。
となんとなく感じてしまったんですね。
先生からの言葉に、疑問を抱いた
また、成績が下がったことや
理解があいまいなまま進んでいることを相談したとき、
先生から返ってきたお言葉が、
「この時期(小4)は、学習習慣が身についていれば十分です」
という一言でした。
たしかに一理あるとは思います。
ただ、
そばには「出来ている」子がいて、
それを見ていて”もっと努力したい”と
感じている我が子に対して
「分からないまま進んでいる状態をそのままにしていいのか?」
と考えると、どうしても納得がいきませんでした。
「やる気はあるのに、学びが前に進んでいない」
そう感じたことが、転塾を本気で考えたきっかけでした。

早稲アカの熱意
実は、早稲田アカデミー以外にもいくつかの塾を検討しました。
- お問い合わせをしてみたものの、電話対応がものすごくお客様対応だったり…
- 体験授業の説明会でしっくりこなかったり…
そんな中で、
「ここだけは空気が違う」と感じたのが早稲アカでした。
体験授業で、衝撃を受けた
早稲アカの体験授業に参加したとき
息子はしょんぼりして帰ってきました。
息子は日能研では上位のGクラスにいたのですが
早稲アカの授業ではまったくついていけなかったようで。
帰宅後に焦った表情でこう言いました。
「全然できなかった。周りの子、めちゃくちゃできてた…」
親としては複雑な気持ちでした。
でも、同時に
「これが外の世界なんだ」と
痛感した瞬間でもありました。
もちろん、習っている単元が違うので、
習っていないところで出来ないのは当然。
それでも、本人を本気にさせる負荷としては
最高の経験だったんじゃないかな?
と、私は感じました。
日能研・早稲アカ 授業スタイルの違い
早稲アカは、先生の一人ひとりがとても熱心で
子どもに対する声かけや反応が的確でした。
そして何よりも印象的だったのが、
「私たちは“結果”で勝負しています」
というスタンスです。
中学受験は、やはり
「合格」という結果が必要な世界。
その現実から目を逸らさずに
毎年実績を更新している姿勢に
私は信頼が持てました。
もちろん、日能研の
”自分で学習出来る子を育てる”
みたいなスタンスも
長期的なスパンで考えた時は
ごもっともで魅力的。
私も、子どもたちには
ひとつひとつ、ていねいに
自分で考えて動ける人間になってほしい
という想いはあります。
でも、中学入試を目的に選ぶ塾
として考えた時、
どちらを、今、優先するか?
という疑問にぶち当たったんですね。
最近の次男を見ていて、今のこの子には
「しっかりと導いてくれる存在が必要」
という想いがありました。
なので、
実績と、先生への信頼感が
早稲アカに決めた理由となりました。
息子も「先生が言ってたから、やってみる」と
素直に受け入れるタイプなので、
人との相性が何より大きいと思ったんですね。
…とかいいつつ、実はまだ通ってません(笑)
ここまでお読みいただいた方の中には、
「実際に通ってみてどうだったの?」と
思われる方もいらっしゃるかと思います。
スミマセン、実は、この記事を書いている現在
息子はまだ早稲アカには通っていません。
日能研の前期は2月から7月までで、
それを一区切りに退塾し
夏期講習から早稲アカに切り替える予定です。
もちろん、
授業のスピードに対する不安はあります。
体験授業のときにまったく歯が立たなかったことは、
正直、親としても動揺がありました。
でも、早稲アカには
「フォローする体制がある」と説明を受けたのと、
「夏期講習は、どんな子なのか様子を見させてください」
とも言っていただきました。
つまり、個人をちゃんと見てフォローして頂ける。
そう感じて、とても心強く思いました。
この夏は、
あえて親が細かくコントロールせず
先生方の手腕を信じてみようと思っています。
「転塾」は逃げじゃない。選び直しは前向きな行動
これから新しい塾に通い始める我が家が
今言えることは一つ。
「転塾は子どもにとって“より良い場所”を見つけるための選び直し」
ということです。
塾のカラーや方針は本当にさまざまで
子どもによって合う・合わないは当然あると思います。
日能研が合う子もいれば、
早稲アカがぴったりの子もいる。
日能研が合う子もいれば、
早稲アカがぴったりの子もいる。
大事なのは、やはり
「自分の子どもに今、何が必要なのか」を
きちんと見つめること。
その判断ができたなら、どんな決断であっても
きっと後悔にはつながらない——
そう思っています。
ちなみに、我が家の長男は
日能研が大好きでした。
卒業してからも、
理科担当のU先生との出会いを
今でも誇らしそうに話してくれます。
現在通っている中学では数学で学年1位を取っていて、
本人は「それも日能研のおかげ」と話しています。
何より、長男が日能研で学んだのは
知識だけではありません。
「勉強って面白い」と思える心を
育ててもらえたこと。
それだけでも、中学受験という経験には
大きな意味があったと思っています。

おわりに|次回は「通ってみてどうだったか」を記録します
今回は、日能研から早稲アカへ転塾するまでの流れと
我が家が感じた葛藤や決断の理由について書きました。
今はまだ、期待と不安の入り混じった
“新しいスタート地点”に立ったばかり。
でも、子ども自身が
「やってみたい」「がんばりたい」と
思ってくれていることが、何よりの希望です。
またしばらくたって、
「実際に通ってみてどうだったか」
「子どもはどんな風に変わったか」についても
追って書いていこうと思います。
同じように悩んでいる誰かの
少しでもヒントになれば嬉しいです。
お読みいただきありがとうございました!
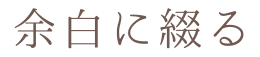




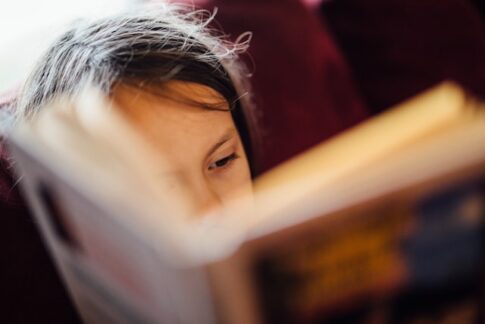






コメントを残す