Contents
帰省中に子供が態度を変える瞬間
お盆や長期休暇に
子供と一緒に実家へ帰省する方も多いのではないでしょうか。
私も今年の夏、長男と次男を連れて
実家に帰省してきました。
久しぶりに祖父母と会えるということもあり
子供たちは朝からワクワク。
荷物の準備も自ら進んでやり遂げ、
出発の時には笑顔が弾けていました。
しかし
実家で過ごす中で
次男の態度に少し戸惑う出来事がありました。
普段は見せない言葉遣いや行動をしてきたのです。
思えばそれは、
「じいじ」という味方がそばにいることや
実家特有の安心感が背景にあったのだと思います。
今日はその時のエピソードと
心理学的に見た背景
そして私自身の対応や学びをまとめてみたいと思います。
久しぶりの祖父母との再会で高まる安心感
飛行機で帰りました。
飛行機好きの長男と、
空港の雰囲気が好きな次男。
中学1年生と小学4年生の男兄弟ですが、
道中は仲良く楽しく過ごしていました。
バスや電車を乗り継いでやっと実家に着いた時
私の声は届かなかったようで、
荷ほどきもしないで
じいじとばあばのいるリビングで楽しそうに話している次男。
この高揚感と安心感が、後に
次男の行動に影響を与えることになるとは
その時はまだ気づいていませんでした。
宿題で見せた次男の予期せぬ言動
帰省中も学校の宿題は待ってくれません。
夏休みの宿題は、少しずつ進めてほしいものです。
その日も私は何気なく次男に聞きました。
私「宿題は進んでる?」
すると、いつもなら
「まだやってない」とか
「あとでやる」と答えるはずの次男が、
驚く言葉を返したのです。
次男「したって言ってるじゃねーかよ」
一瞬、耳を疑いました。
まるで漫才のツッコミのような、
強めでくだけた口調。
しかも、少し馬鹿にするニュアンスも感じました。
普段はそんな言い方をしない子なので、
私の中でザワッと何かが動きました。
その場にはじいじがいて、
特に咎めることもなく笑っていました。
場の空気は和やかで、
険悪になる雰囲気はありません。

私が取った対応と気づき
感情的に叱らず受け流す判断
その場で私は思わず
私「調子に乗るな!」
と怒鳴ってしまいました。(笑)
しかし次男は2度3度と同じことを繰り返します。
そこで私は感情を冷まし、
表面的には受け流すことにしました。
しかし内心では「なんでそんな言い方を…?」
というモヤモヤが静かに残っていました。
その時の私の心の動き
母親としての違和感と悲しさ
祖父母の前での出来事ということもあり
私の中には2つの気持ちが同時にありました。
ひとつは、母親としての違和感や悲しさです。
信頼関係のあるはずの親子の会話で
見下すような口調が出てきたこと。
これまで築いてきた関係が一瞬で揺らいだような気がして
胸がチクリとしました。
場の空気を壊したくない思い
もうひとつは、
場の空気を壊したくないという思いです。
祖父母にとって孫は可愛い存在。
多少の生意気さも「子供らしい」と
微笑ましく受け止められることがあります。
そこで私が感情的に叱ってしまえば
「お母さんは細かい」と映るかもしれない。
そんな迷いもありました。
この2つの気持ちの間で
一瞬立ち止まり、その場ではもう、
何も言わないという選択をしました。
心理学で見る“調子に乗る行動”の背景
優越感が生む誤った安心感
祖父母、特にじいじが全面的に味方になってくれる安心感は、
子供にとってとても大きいものです。
「自分は守られている」という感覚は
時に自信となり、時に優越感に変わります。
この優越感が、
「お母さんに対して少し強めに出ても大丈夫」という
誤った安心を生み出していたのかもしれません。
安全基地効果で挑発的になる心理
心理学でいう「安全基地」とは
安心できる存在がそばにいることで、
子供が新しい行動に挑戦するようになることだそうです。
じいじという安全基地がある環境では
次男は普段よりも冒険的、
時には挑発的な行動に出やすくなっていたのでしょう。
権威の分散による母の影響力の弱まり
家庭では母親の言葉やルールが最優先ですが
実家では祖父母の影響力が加わります。
その結果、子供にとって
「誰の言葉を優先するか」が曖昧になり
母の権威が一時的に弱まることがあります。
この状態を「権威の分散」と呼ぶ
と、以前本で読んだ事を思い出しました。
注目を集めたい子供の行動パターン
子供は注目を集めたい生き物ですよね。
特にうちの次男は
「僕をみて!」タイプのお調子者…。
面白いことを言えば笑いが起き、
場が盛り上がる。
今回の次男の言葉も
「場を面白くしたい」という思いが
根底にあったのではないでしょうか。
ただし、その方向が
母をからかう形にズレてしまったー。
私はそう感じ取りました。
後で二人きりで気持ちを伝える重要性
後日、二人きりになったタイミングでこう話しました。
私「さっきの言い方、お母さんはちょっと腹立たしかったし、悲しかったよ。どういう気持ちで言ったの?」
次男は
次男「そんなこと、言ってないし」
と答えました。
本人に悪意はなかったかもしれませんが、
言葉は相手に影響を与えます。
そのことを、この機会に改めて伝えられたのは
良い経験だったと思う事にしました。

次回の帰省に向けた対策
子供と事前にルールを確認
次回の帰省前に、次男と
- 実家でもお母さんの言葉が優先
- 祖父母と意見が違ったらまずお母さんの話を聞く
というルールを確認しようと思いました。
私だって、イラっとしたくないもの。
祖父母にも協力をお願いする
さらに祖父母にも、
「子供の態度が少し強めになったら、
やんわり注意してもらえると助かる」と
伝えておくつもりです。
こうした小さな準備が、
次回の帰省をより穏やかなものにしてくれる…はずです。(笑)
親として得られた学び
子供の態度は環境で変わる
自宅では見せない言動も
祖父母の前や実家という特別な環境では
出てくることがあります。
それは必ずしも性格が変わったわけではなく
安心感や優越感など
環境要因の影響が強く出ているだけだとわかりました。
叱るタイミングの見極めが大切
感情的に叱るのではなく、
落ち着いた環境で「どう感じたか」を伝える方が
子供の心に届きやすいと感じました。
特に祖父母の前では、
家族間の力関係や空気を壊さない配慮も必要ですよね。
事前のルール共有で混乱を防ぐ
「実家でもお母さんの言葉が優先」
「意見が食い違ったらまずお母さんの話を聞く」
というルールを事前に共有することで、
子供も混乱せず安心して行動できると思います。
その後の次男
今回の事で、何より印象的だったのは
自宅に戻ると次男の“調子に乗った感じ”は
完全に消えていたことです。
これは、態度の変化が一時的なもので、
環境要因が大きかったことの証拠だと思います。
「小4の反抗期…」そんなことも感じましたが、
今回の経験は
「生意気に見える行動も背景には理由がある」ということを
再確認させてくれました。
親としては、その理由を理解し
次につながる関わり方を選ぶことが大切だと感じました。

あなたのお子さんも帰省中に態度が変わることはありませんか?
私は今現在母親13年目ですが、
まだまだ学ぶべきことだらけだなと感じました。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
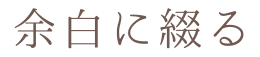






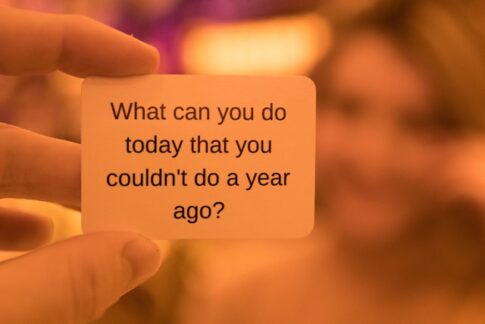




コメントを残す