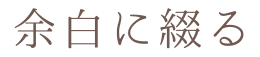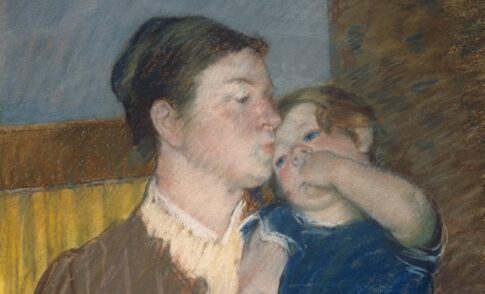「テストの結果が悪かったとき、
つい子どもに厳しく言ってしまう」
そんなこと、ありませんか?
私はあります。
「なんでやらないの?」
「もっとこうすればいいのに」
そう思って
つい口を出しそうになる瞬間が
何度もありました。
でも、あるやりとりを通して
私は大事なことに気づきました。
それは、
「今、目の前にいる子どもを
そのまま受けとめること」の大切さです。
私自身
まだまだできていないことばかりですが、
今回の経験を通して
「これからはこうしていこう」と
思えることがありました。
この記事では
その気づきや学びをシェアしたいと思います。
「うちもそうかも」
「それでいいんだ」
そんなふうに、
誰かの心が少しでもラクになる
きっかけになれば嬉しいです。
- 子どもが「悔しい」と言えたことにホッとした
- 結果よりも気持ちを話してくれたことが嬉しかった
- 「大丈夫!」の連呼がプレッシャーになっていたかもしれない
- 親の関わり方ひとつで、子どもの自信のつき方が全然違う

Contents
テストのごほうびと結果
今回のテストでは、
「4教科でクラス平均点以上とれたら仮面ライダーのお菓子入りフィギュアをプレゼントする」というごほうびを用意していました。(600円くらいの食玩です)
次男は、仮面ライダーのフィギュアを
とても欲しがっていました。
「ごほうびがあるから頑張る」
という単純な話ではなく、
それが
“自分で目標を決めて努力する体験”
につながればいいなと思っていました。
そして今回は、テスト本番まで
「あれやった?」「これ忘れてない?」などと
口出しするのをぐっとこらえて、
学習計画も含めて全部本人に任せてみました。
結果として・・・
子どもはテスト勉強をほとんどしないまま
本番を迎えてしまい、
当然ながらごほうびの条件には届きませんでした。
本人はがっかりしていましたが、
ここからが本当の“学び”の始まりだった気がします。
ごほうびがもらえなかったことは、
本人にとっては小さな失敗だったかもしれません。
でも、「悔しい」という気持ちや
「次は頑張ろうかな」という
前向きな気持ちを引き出すきっかけになったような気がします。
ごほうびは“目的”ではなく
“きっかけ”にすぎなかったけれど、
その役割は果たしてくれたと思います。
そして私は今回、改めて
「親の心構え」を考えさせられました。
ごほうびを設定すること自体が
“条件付きの愛”になっていないか?
勉強を“ごほうびのための手段”
にしてしまっていないか?
ごほうびを活かすも殺すも、
結局はその後の関わり方次第。
これは今後も意識していきたい
大切な視点だと思いました。
「悔しかった」の一言に見えた本気
(仮面ライダーゲットできなくて)
「悲しかったのかな?」と私がたずねると、
返ってきた言葉は悔しかった」
でした。
これを聞いて、私はむしろ安心しました。
悔しいと思えるのは、
それだけやりたかった・できたと思っていたから。
ちゃんと気持ちが向いていた証拠
だと感じました。
そして何よりも、
「できなかったときの気持ち」
を話してくれたことが、
本当に嬉しかった。
長男のときはこんなふうに
気持ちを引き出すような対話が
できていなかったな…と、
私にとっても大きな反省と
学びの瞬間でした。
長男が同じような年頃だった頃、私は
「ちゃんとやったの?」「次は頑張ろうね」
と、つい“評価”や“指導”
の目線でばかり声をかけていた気がします。
本人の感情に寄り添うというより
「次にどうするか」ばかりを考えていて…
当時の長男の気持ちを聞き出す余裕が
私にはなかったのだと思います。
気持ちを聞いてもらえなかったことで、
長男はどんなふうに感じていたのだろう?
本当は彼の心にも
「悔しい」があったのかもしれない。
だけど、それを言葉にする機会を、
私が奪ってしまっていたのかもしれません。
今回、
次男が「悔しかった」と
自分の気持ちを言えたことで、
私自身もようやく“聴く姿勢”を
少しは持てるようになったのかもしれない…
そんなふうに思いました。

勉強は好き。でも間違うと凹む子ども心
「勉強は好きなんだよ」と本人は言います。
でも、
間違えて直しをしなければならない時に、
ものすごくがっかりしてしまうらしい。
その理由を本人なりに言葉にすると、
「間違えていた=自分はできていない=ダメなところを直さなきゃいけない」
という思考回路になるみたいです。
できなかった自分にがっかりして、
直しをしながらどんどん気持ちが落ちていく…。
最初は楽しんでいたのに
間違いに出会った瞬間、
テンションがガクンと下がる。
そんな様子を見ると、
こちらも胸がキュッとなります。
“好き” と “得意” は違うし、
“好き” だからこそ余計に
「うまくできなかった自分」にショックを受ける。
その気持ちは、
実は大人でもよくあること。
私も昔、好きなピアノで
ミスをしては落ち込んでいたことを思い出しました。
完璧にこなしたい気持ちと、
失敗への耐性のなさ。
その間で揺れているのが、
今の子どもの心なんだと思います。
だからこそ
「間違えても大丈夫」というメッセージを
もっとさりげなく、日常的に伝えていけたらいい。
テストの点数や正解率ばかりに目が向きがちだけれど…
「間違えるって、伸びしろなんだよ」
という考え方を
一緒に少しずつ育てていきたいです。
「キミなら大丈夫!」の落とし穴
私はいつも、
「キミなら絶対できる!」「大丈夫!」
と声をかけていました。
励ましのつもりだったけれど、
今思えばそれが子どもにとっては
プレッシャーだったのかもしれません。
最初は、失敗した本人から
「ママのせい」と言われてびっくりしました。(笑)
なんでやねん!と思いながらも
詳しく聞いてみると…
私が“松岡修造ばり”に
「キミは大丈夫!」と連呼していたことが原因らしい。
それを聞いて、ハッとしました。
私は「信じてるよ」の気持ちを伝えたくて、
言葉にしていただけ。
でもそれが、
本人にとっては
「大丈夫って言われてるから、自分はできるはず」
と思い込み、努力する必要性を
見失うきっかけになっていたのかもしれません。
実際、今回のテスト前も
「自分はできる」と本気で信じていました。
でも現実には、ほとんど勉強しなかった。
そして当然ながら、
結果も伴わず大ショック。
「信じていた自分」と「結果のギャップ」に
本人は大きなショックを受けたと思います。
その姿を見て、私はようやく気づきました。
応援の言葉は、
タイミングと中身が大事なんだということを。
「キミは大丈夫!」という言葉の裏に
「努力してるキミを見てるよ」
「積み重ねたことは裏切らないよ」といった
“プロセスへの信頼”が伴っていなければ、
単なる“根拠のない期待”になってしまうのだと。
だから、
これからはただ「大丈夫」と言うのではなく、
「この前よりもノートに向かう時間が増えたね」
とか
「前は間違えた問題、今回は解けてたね」など
具体的な努力や変化をちゃんと拾って
声をかけていきたいと思っています。
今回、私がぐっとこらえたこと
私自身が中学受験をしたころは、小学校では
自分でも誇れるくらいの優等生でした。
成績も良く、完璧主義な部分も強かったため、
「なぜできないのか」が正直理解できないところがありました。
だからこそ、子どもが思うように
結果を出せない姿を見ると、
「どうしてもっと頑張れないんだろう」と
ついイライラしてしまう自分がいました。
でも、
今回はその気持ちをぐっとこらえました。
自分の基準を一旦脇に置き
子どもが今感じていることや、
なぜうまくいかなかったのか、
その理由をしっかり聴こうと決めたのです。
完璧主義だった私には理解しにくいからこそ、
「これは私の感覚や価値観であって、
子どもには子どものペースや感じ方がある」
ということを強く意識しました。
正直、「こうあるべき」「こうしなければならない」という
自分の枠から外れるのは、
簡単なことではありませんでした。
しかし、
「自分の理想と子どもの現実は違う」という事実を受け入れ、
怒りや焦りをぐっと抑えたことで、
子どもとのコミュニケーションが
ずっとスムーズになったのを実感しました。
子どもも素直に気持ちを話してくれて、初めて
「こういう気持ちで頑張っているんだ」と
知ることができました。
これは私にとって大きな学びです。
完璧主義だった自分の基準に縛られず、
子どもそれぞれの成長のペースを尊重すること。
以前の私なら、
「なんで勉強しなかったの!」
「ほら見たことか」と言っていたと思います。
でも今回は、
まず子どもの言葉を待ち
「どう思った?」「どこが悔しかった?」と聞いて、
本人の気持ちに寄り添うことを
最優先にできた気がします。
この
“ぐっとこらえる”
ということが
本当に難しいけれど、
本当に大切なんだと改めて実感しました。

これからの関わり方について
今回の経験を通じて、私が強く感じたのは
「子どもに対してまずは耳を傾けることの大切さ」
です。
完璧主義だった自分の基準を一旦置き、
子どものペースや気持ちを尊重することで
これまでよりもぐっと深いコミュニケーションが生まれました。
これからは、
結果だけを見るのではなく、
その過程で子どもが何を感じ
どう考えているのかをもっと大切にしていきたいと思います。
たとえ、成績が思うように伸びなくても
「頑張ったね」と認め
失敗や挫折も成長の一部として受け入れる姿勢で
接したいと思っています。
また、
自身が感じた焦りや苛立ちをぐっとこらえることで、
子どもに安心感を与えられる関わり方を目指します。
子どもが心を開きやすい環境をつくることが、
将来的には本人の自立や自己肯定感の向上にもつながると信じています。
完璧な親であろうとせず
時には私自身も迷いながら、
一緒に歩んでいく関係を築いていきたい。
それが、今の私にとって最も大切な
“これからの関わり方”だと感じています。
まとめ:失敗の価値と、親としての一歩
これからは、結果だけを見るのではなく
「その過程で子どもが何を感じ、
どう考えているのか」
ということに目を向けていきたいと思います。
努力の積み重ねや小さな変化を認め、
具体的に伝えることで、
子どもの自信と自己肯定感を育てていく。
そのためには、親自身も完璧を求めすぎず
子どものペースに寄り添う余裕を持つことが
必要だと感じています。
「なんでやらなかったの?」という問いかけを飲み込み、
まずは静かに聴くという選択をすることで、
子どもは安心して心を開きやすくなります。
その安心感が、
次の一歩を踏み出す力につながるのだと思います。
子どもも親も、完璧ではないからこそ
一緒に成長し合えるのだと改めて感じました。
子どもの気持ちにしっかり寄り添いながら
完璧を求めすぎず
「今のがんばり」を認めてあげる。
親としてできることは、
失敗を恐れず挑戦し続けられる環境を整えること。
そのためにも、
自分の完璧主義を少し緩めて、
子どもの成長を温かく見守っていけたらいいな
と思いました。
最後までお読みいただきありがとうございました!