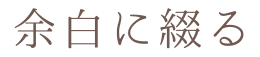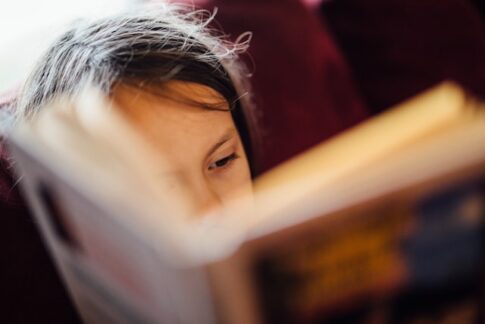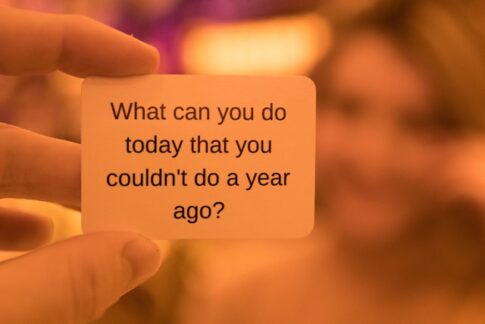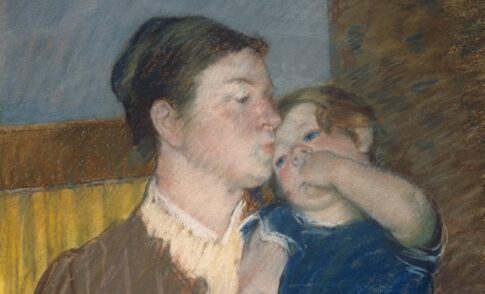最近、小学4年生の次男がなんだか騒がしいんです。
いや、彼の存在自体は
ずっとにぎやかだったのだけど…
ここ最近は特に
「見て!」「聞いて!」
「なんでそんなこと言うの!?」と、
感情の起伏が激しい。
素直になったかと思えば、
次の瞬間にはブチ切れている…
最初は
「反抗期かしら…」と身構えたけれど、
観察していくうちに気づいたのです。
これ、全部
「認めてほしい」アピールだったのでは?と。
ちょっと笑えて、
ちょっとしんどくて、
でも学びもあった。
今回は、そんな
“アピール上手な小4男子”との日々を通して、
親として感じたことを綴ってみます。
- 子どもの“キレ”の奥にあるのは、未処理の「見てほしい」気持ち
- 褒められると照れるけど、ちゃんと心には届いている
- 自己肯定感は、親の「気づき」と「ひと言」から育つ
Contents
小4男子、急に怒るのなんで?
ある日、学校から帰ってきて早々
「これ、おいらが学校で作ったんだ!」と
図工の作品の写真を見せてきた次男。
(うちの次男の一人称は”おいら”です笑)
私がちょっと上の空で
「わー、いいじゃーん」と返したその3秒後。
「もういい!
ママなんかに見せなきゃよかった!!」
唐突なブチ切れ。
私はわけがわからず
「え、なに!?」と聞き返すと、
ドンドンと床をたたくように歩いて去っていき
ドアをバタン!!
追いかけて理由を聞くと…
「どうせ見てくれてないからいいよ!」
と。
いや、3秒では心の準備ができなかったんだよ
母は…。
ここで私はようやく気づきました。
「あ、これは“作品の紹介”じゃなくて、
“おいらを見て!”なんだ」と。
次男のアピールは、
思った以上にエネルギーを使う自己表現だったのです。
アピール上手な次男の一言に気づく
「おいら、今日塾のテストで悪い点とった」
「でもテストの前に復習頑張ってた」
そんな一言に、
「ん?それって、どっちが言いたいんだろう?」
と考え込んだある日。
つまりこれは・・・
“結果は出なかったけど頑張った自分”を
認めてほしいってこと。
「結果が悪かった」ことも伝えたい。
けれどそれ以上に、
「努力してた自分」をわかってほしい。
次男のこの手のアピール、
よくよく聞いていると随所にちりばめられていて
「テスト悪かった」という悲報のあとには
必ずと言っていいほど
“フォロー情報”がついてくる。
「でも、前日は早く寝た」
「でも、3ページは見直した」
みたいな。
これ、
本人なりの全力のアピールなんですよね。
“がんばったのに報われなかった”
っていう、小4なりの葛藤。
そして
「それでもちゃんとやったもんね!」
と誰かに言ってもらいたい気持ち。
なので私は、
結果を責めるのではなく、まず
「ちゃんと復習してたんだね」と
私の気持ちに余裕がある時は可能な限り
“努力の方”を先に拾うように
と決めました。

「それってさ、ちゃんと前もって
準備してたってことでしょ?さすが!」
と返すと、次男はちょっとうなずいて、
「でもさー、
やっても無駄なんじゃないかとも思ってる」
とポツリ。
出た、
「俺やっても無駄なんだよ」発言。
これ、小4男子あるあるなんでしょうか
「努力したけど結果が出なかった=もうやらない」
という極端理論。
でもそこで、「無理してやらなくていい」
などと言ってしまうと、
可能性の芽を摘んでしまう…
なので私は、
結果を責めるのではなく、まず
「復習してたんだね」と
“努力の方”を先に拾うようにしました。
すると彼は、
「だって今回は、
理科の植物が難しかったんだよ」と
自分なりに振り返りを始める。
そして最後には
「次はもっとちゃんと復習するわ」
と前向きなひと言。
(やるかどうかは別として、ね…。)
あぁ、これは今まさに
「自己肯定感」を育てるタイミングなんだ――
そう気づかされた瞬間でした。
褒め方、叱り方で変わる“その後”
子どもが何かを頑張ったとき
私はつい「すごいじゃん!」と
テンプレ反応してしまう。
でも最近はそれより、
「◯◯を工夫したんだね」
「ここ、自分で考えたの?」と
“具体的に見る”ことが大事だと感じています。
逆に
感情的に怒ってしまうと、
次の日まで引きずるのがうちの次男。
次男の場合、しばらく
「朝の準備しない」「無言で学校に行く」などの
小さな“抗議活動”に出ます。
(地味に効くやつ…。)
褒めても叱っても、
「どれだけ“自分を見てくれているか”」が
彼の中での評価軸になっているようです。
「認める」ってどうすればいいの?
「認める」ってなんだろう。
子どもにとって、それは
「存在をちゃんと見てもらうこと」。
「頑張ったね」だけじゃなく、
「悔しかったんだね」
「自分で決めたんだね」と
感情や行動の“背景”を言葉にしてあげると
ぐっと心が落ち着いてくるように感じます。
本人はそのとき照れたり、
否定したりするけれど
あとからひょっこり寄ってきて
「さっきのさ、ちょっと嬉しかった」
とポツリと言ったりもする。
あれはたぶん、彼なりの
最大級の“ありがとう”なのだと受け取っています。
子どもの自己肯定感は親の“ひと言”から
自己肯定感といえば、
実は私自身
あまり高くない方だと思っています。
小さなころから、母に
「あれしなさい」「これしなさい」と
言われ続けて育ちました。
主に勉強のこと。
母が喜ぶかなと思って、
一生懸命やってきたつもりです。
でも思い返してみると、
母は私をちゃんと“見て”いたのかな、
と思うのです。
私の努力や気持ちよりも、
「母の基準」でしか評価されなかった
ように感じていました。
しかも、
その基準は気まぐれで
期待どおりの結果が出ないと
怒られることもしばしば。
だから私は
「何をどう頑張っても、
認められないんじゃないか」
と思うようになっていった。
そんな母の姿を見て育ったからこそ
私は自分の子どものことは
「ちゃんと見ていたい」と思っています。
何ができたか、何点だったかではなくて、
「そのとき何を感じていたのか」
「どう工夫したのか」
そこに目を向けて、
ひと言でもいい声をかける。
それだけで、子どもが自分で
小さな自信の芽を育てていくんじゃないかな?
と今の私は信じています。

現に最近、次男が
「オレ、〇〇してみようかな」
と言う場面が増えてきました。
自分で選んで、自分で動こうとしている。
そこには、小さな自信が
芽生え始めているように見えます。
その自信の種は、きっと
「自分を見てくれている」という安心感の中で育つのだと、
私は思います。
子育てって、失敗の連続だし
笑っちゃうほど思い通りにいかない。
でも、笑いながら気づいて
また関わり方を変えてみる。
そんな日々の中にこそ
子どもの「自分って悪くないかも」を
育てるヒントが詰まっている気がしています。
まとめ
- 子どもの“キレる”は、「見て」「わかって」の裏返し
- アピールの言葉の裏側にある“本音”に気づいてあげると、反応が変わる
- 「認める」とは、結果ではなく“過程”や“気持ち”を言葉にすること
- 照れながらも心に届いているその言葉が、子どもの自己肯定感を育てるはず!
今日も次男は
「おいらの話、ちゃんと聞いてた!?」と
キレながら寄ってきます。
うん、聞いてたよ。(いや、聞いてない時もあるけど)
でも、ちゃんと見ようと努力してるよ。
だから大丈夫、きっと大丈夫。
私が子どものころにずっと欲しかった
“言葉”や“まなざし”を
いま、私がわが子に届けている。
そう思うと、
ダメダメだらけの私の子育てはちょっと報われるし
自分自身も少しずつ満たされていくような気がします。
「ちゃんと見てるよ」
そのひと言が、
子どもにとっても自分にとっても
いちばんの安心になるのかもしれません。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!