Contents
「嘘つき」——そう思った日のこと
「ちょっと変なものが入っていないか確認してくるね」
そう言って
次男はお友達へのプレゼント用にラッピングした袋を持って
自分の部屋へと消えていきました。
まるでなにかの点検をするような…
そんな自然なふるまい。
けれど
私はすでにその中身を知っていました。
袋の中に入っていたのは——
夫(つまり次男の父)からもらった
ハンカチでした。
あれ?と、ん?と、もしかして?の間で
ことの始まりは
「お友達の誕生日に何をプレゼントするの?」
と聞いた何気ない会話でした。
次男はにっこりと笑いながら
こう答えました。
「お金を貯めて、自分で買ったハンカチだよ」
その瞬間
「あれ?なんか変だな」と思った私の胸に
ざわざわとした違和感が湧き上がってきました。
ついさっき、家の中で見かけたあの
ラッピングの袋の中身を…
私は偶然見ていたのです。
中に入っていたのは、間違いなく
父からプレゼントされたハンカチ。
新品だけれど、家にあるもので
次男が自分で買ったものではない。
「ああ、これは……嘘だな」
瞬時にそう理解したものの
私はその場で問い詰めることはしませんでした。
代わりに、少し様子を見ることにしました。

嘘をつく息子に、私はどう向き合えばいい?
「うちの子はよく嘘をつく…」
これまでも
些細なことから大きなことまで
何度も「嘘」にまつわる場面に直面してきました。
宿題をやったふりをしたり
忘れ物をごまかしたり
帰宅が遅くなった理由を作ってみたり
ちょっと話を盛ったり——。
子どもだからしょうがない。
でも、
なんでこんなに頻繁に嘘をつくの?
どうして正直に言えないの?
信じたいのに、信じられない。
そんな葛藤の中で
私はたびたび迷子になってきました。
嘘を見破ったとき
親としての私の対応はいつも揺れます。
叱るべきか、そっと見守るか。
問い詰めるべきか、
自分で気づくのを待つべきか。
この日も、その揺れの中で
私は静かに次男の言動を見つめていました。
予想外の「すり替え」
やがて次男が部屋から戻ってきたとき、
袋の中に入っていたのは——
今まで自分が使っていた
くたびれたハンカチでした。
えっ。
一瞬、言葉を失いました。
思わず二度見しました。
「え?これ……さすがに
プレゼントにはできないよね?」
私は、笑いそうになるのをぐっと堪えながら
そう言いました。
本人も、何となくバツの悪そうな顔をしています。
でも、
「どうしてすり替えたの?」とも
「最初はお父さんのハンカチだったよね?」とも
私は言いませんでした。
たぶん、本人も
バレてることには気づいていたはず。
けれど、
「嘘をついた」と自分で認めることは
どうしてもできなかったようです。
「嘘」は悪なのか?
そもそも
嘘ってどう扱えばいいんでしょう。
私自身、大人になる過程で
たくさんの「嘘」を見てきたし
自分でもついたことがあります。
「バレないだろう」という軽い気持ち。
「その場をやり過ごしたい」という逃げ。
「傷つけたくない」という優しさのつもり。
「自分を大きく見せたい」という願望。
嘘って、実はけっこう
感情が複雑に絡んでいるんですよね。
子どもの嘘も、同じです。
次男もきっと——
- お金がなかったけど、プレゼントを用意したかった
- 「自分で買った」と言いたかった(もしかしたら、友達にそう言うことでカッコつけたかったのかもしれない)
- 誰かにばれないと思っていた
- ばれたとしても、その場をしのげばいいと思っていた
こんな気持ちがいろいろ絡み合って
でも
それを言葉にする力もまだなくて。
だから
「嘘」でつじつまを合わせようとしたんだと思います。
謝ることより、どう行動を修正するか
この出来事の中で
私が一番印象に残っているのは
「ごめんなさい」とは言えなかったけれど
「中身を変えた」という次男の行動でした。
「これじゃまずい」とどこかで思って、
でも認めるのは怖くて、だから
せめて内容だけでも変えようとした。
これ、私にとっては
すごく意味のあることだったんです。
「うちの子、反省しない」
「謝れない」「嘘をつく」
……それだけを見れば
マイナスにしか見えないかもしれません。
でも、
行動を変えようとする
小さな一歩を見逃さなかったとしたら、
私たち親は、子どもにとって
「安全な着地点」をつくってあげられる存在に
なれるかもしれない。
嘘をつかせない家庭より、嘘を隠さない関係を
私はこの一件を通じて
ちょっと思い直しました。
「嘘をつかない子に育てたい」
というのは、理想だけれど…
現実には無理があるかもしれません。
それよりも、
- 「嘘をついてしまったことを隠さなくてもいい」
- 「本当のことを言っても、ちゃんと受け止めてもらえる」
そんな関係性のほうが
ずっと大切なのかもしれないって思うんです。
もちろん、嘘はいけないこと。
他人からの信頼を欠く行為ですもの。
でも、
嘘をつく子どもを「ダメ」
と切り捨てるのではなくて、
「どうしてその嘘を選んだのか」
を知ろうとすること。
そして、誠実に行動し直せたときには
ちゃんと評価してあげること。
それが、嘘をつく子どもを
「信じる」ってことなのかもしれないな。
と思うんです。

正解?不正解?
今回の件が“正解”だったのかどうかは
正直私にはわかりません。
謝らせなかったことが良かったのか、
それとも、もっと厳しく向き合うべきだったのか。
でも、
「嘘つき!」と怒鳴らずに済んだこと。
彼の中での“軌道修正”を、
ちゃんと見届けられたこと。
それだけは、自分の中では
よかったと思っています。
私も、まだまだ模索中です。
「どうすればいいの?」
「これでよかったの?」と…
答えの出ない問いに向き合いながら、
でも、やっぱり
この子と向き合っていきたい、そう思っています。
さいごに:嘘を責めずに、関係を育てていくために
子どもが嘘をついたとき
私たち親は
「その嘘が悪いことだ」とわかっているからこそ
心がざわつきます。
でも今回、
私は息子の嘘をただ「悪いこと」として片付けず、
その裏にある気持ちや
行動の変化をじっくり見つめることができました。
謝れなかった息子。
だけど、自分なりに中身をすり替えて
別の形で誠実に渡そうとした姿。
その奥にある、
「これじゃだめだ」「どうにかしたい」
「やり直したい」という気持ちは
ちゃんと伝わってきました。
子どもはまだ、
自分の気持ちを言葉でうまく伝えられません。
だからときに、嘘やごまかしという形で
気持ちを守ろうとするのかもしれません。
嘘をなくすことよりも、
「本当のことを言っても大丈夫な関係」を
少しずつ築いていくこと。
それが、今の私にできることなのかな
と思っています。
そして何より、親である私も間違えるし
揺れるし、まだまだ模索中です。
だからこそ、
「完璧な対応」より
「一緒に成長していく姿勢」を大切にしたい。
子どもの嘘に悩むことがあったとき、
今回の出来事を思い出しながら
また一歩ずつ進んでいけたらと思います。
今回もお読みいただきありがとうございました。
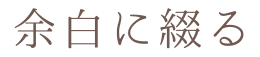




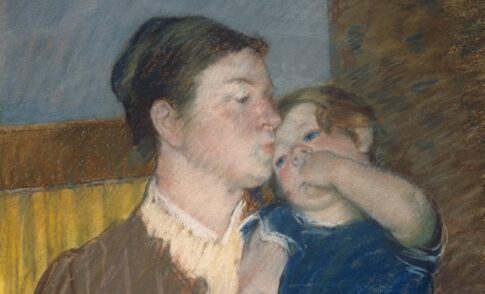



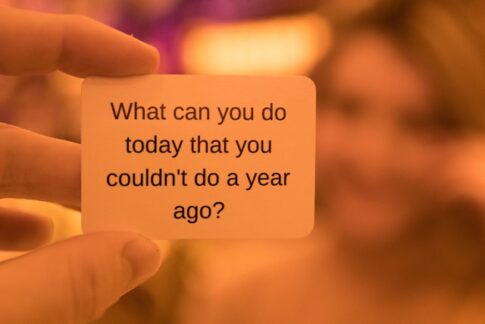


コメントを残す